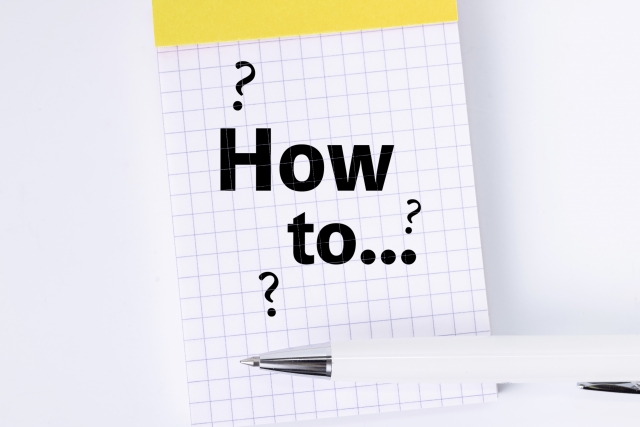自転車の青切符制度とは?2026年から何が変わるのか
2026年4月から、自転車の軽微な交通違反にも「青切符(交通反則通告制度)」が導入されます。
対象となるのは16歳以上で、違反内容に応じて反則金が科される仕組みです。
これまで注意や講習で済んでいた行為にも金銭的な罰則が発生するため、日常的な乗り方の見直しが求められます。
青切符の対象年齢
16歳以上が対象です。未成年でも違反すれば反則金が発生します。
一時停止は徐行でも違反になる
徐行では違反になります。必ず完全停止し、安全確認を行いましょう。
歩行者信号が青なら自転車も渡っていい?
歩行者専用信号のときは、自転車は降りて押して渡る必要があります。
並走やイヤホンは許される範囲はある?
並走は原則禁止。イヤホンは音量次第で違反とみなされることもあります。
生活道路の30km/hは標識がない道も対象
基本はすべて対象ですが、速度標識がある場合はそちらが優先されます。
自転車の青切符で反則金はいくら?代表的な違反と金額一覧
自転車の違反は積み重なると高額になることがあります。
以下は主な違反例と反則金の目安です。
| 違反内容 | 反則金の目安 | 補足・注意点 |
|---|---|---|
| スマホ操作 | 約12,000円 | 前方不注意による事故リスクが高い |
| 信号無視 | 約6,000円 | 歩行者専用信号では進行不可 |
| 右側通行・歩道の無許可走行 | 約6,000円 | 軽車両のため左側通行が原則 |
| 一時停止無視 | 約5,000円 | 必ず片足を地面につけて完全停止 |
| 傘差し運転・片手運転 | 約5,000円 | 傘ホルダー利用も自治体によって異なる |
| イヤホン・ヘッドホン使用 | 約5,000円 | 音量が大きいと警告音が聞こえず危険 |
| 無灯火走行 | 約5,000円 | 点灯は義務。点滅ライトは補助用 |
| 二人乗り | 約3,000円 | 子ども乗せ専用以外は原則禁止 |
| 並走走行 | 約3,000円 | すれ違い・追い抜き時に危険を伴う |
複数の違反を同時に行うと、合計2〜3万円に達することもあります。
例えば「無灯火+並走+イヤホン走行」で約13,000円、さらに「スマホ操作」が加われば25,000円以上になるケースも。
学生や通勤者も対象になるため、家庭や職場で早めの意識共有が必要です。
反則金を避けるための5つの基本ルール
1. 一時停止は必ず完全に止まる
白線の手前でブレーキをかけ、片足を地面につけて左右を確認。
「徐行」ではなく“停止”がルールです。
2. イヤホンやスマホ操作は乗る前に完了
目的地設定・音楽操作は停車時に行いましょう。
骨伝導タイプでも音量が大きいと周囲の音が聞こえにくくなります。
3. 夜間は常時ライトを点灯
夕方や曇天でも「早め点灯」を習慣に。
ハイビジ色の服や反射グッズも有効です。
4. 歩道は“例外”として考える
自転車は車道の左端が基本ルート。
歩道を通るときは歩行者優先・徐行が鉄則です。
5. 傘は使わずレインウェアを活用
傘差し運転はバランスを崩しやすく非常に危険です。
雨の日はレインコートやポンチョに切り替えましょう。
生活道路の法定速度30km/hへ|いつから・どこで適用される?
2026年9月から、住宅街などの生活道路では原則30km/h制限が導入されます。
ただし、高速道路や中央分離帯のある幹線道路などは対象外です。
「標識がなければ30km/h」と覚えておくとわかりやすいでしょう。
なぜ30km/hに引き下げるのか
生活道路では、歩行者・自転車との距離が近く、事故時の致死率が速度で大きく変わります。
時速30kmなら助かる可能性が高く、50kmでは致命傷になることもあります。
速度を抑えることで事故の重傷化を防ぐ狙いがあります。
自転車を追い抜くときの新ルール
2026年4月以降、自動車が自転車を追い抜く際は“安全な速度と間隔”を確保することが義務化されます。
目安としては側方1〜1.5mの距離を取り、十分に減速するのが安全です。
道幅が狭い場合は無理に追い抜かず、タイミングをずらす判断も大切です。
原付の新制度「新原付」とは?
環境基準の強化により、従来の50ccバイクは段階的に姿を消します。
代わりに導入されるのが「新原付」で、原付免許で125cc以下・最高出力4.5kWまでの車両が運転可能になります。
ただし、最高速度は30km/hのまま。パワーがある分、操作ミスにはより注意が必要です。
まとめ|安全運転が最大の節約になる
2026年は、自転車や生活道路のルールが大きく変わる年です。
青切符による反則金を避ける最善策は、日常的に安全運転を徹底すること。
「完全停止」「早め点灯」「ながら運転禁止」など、基本を守るだけで罰金も事故も防げます。
ルールを知ることは、自分と周囲の命を守る第一歩です。