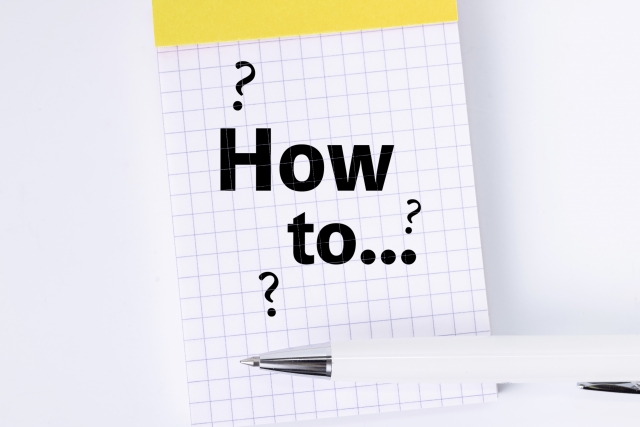SNS上で「お店のカレーに具が入っていなくてがっかり」という投稿が話題になりました。
これに対して、実際の飲食店経営者が「なぜカレーに具が少ないのか」を丁寧に説明し、納得の声が広がっています。
見た目には“レトルト感が強い”と感じるカレーも、そこには深い理由があるようです。
カレーの具が少ないのは“食中毒防止”のため
投稿したのは、ドライブイン形式の飲食店を運営する「朝日ドライブイン」の社長。
同氏によると、飲食店で具の少ないカレーが多い理由は「食中毒のリスクを避けるため」だといいます。
特に、長時間保温を行う店舗ではウェルシュ菌やボツリヌス菌といった細菌が増殖しやすく、具材を残したままの状態で保存することは非常に危険なのだそうです。
「安全を最優先するため、まずは食中毒を防ぐこと。そのうえで味を追求している」と社長は説明しています。
大きな具材を入れて長時間保温するほうが、実はずっとリスクが高いというわけです。
ココイチ方式が「理にかなっている」と話題に
この投稿に対して、「だからココイチ(CoCo壱番屋)のスタイルが正解なのか」と納得する声が多数寄せられました。
カレーチェーン店の多くは、ルーと具材を別々に管理し、提供時にトッピングとして追加するスタイルを採用しています。
これは、具材を都度加熱して提供できるため、食中毒のリスクを大幅に下げられる仕組みです。
専門店では、ルーと具を別調理し、盛り付け直前に合わせる方法もありますが、一般的な飲食店で同じことを行うとコストや手間が大きくなります。
そのため、具を最初から溶かし込んだり、あえて具なしで提供したりするケースが多いのです。
「具がない=手抜き」ではなく“安全第一”の証
SNSでは「具がないのはレトルト感が強くて残念」という意見の一方で、「衛生面を考えれば納得」という理解の声も増えました。
実際には、具が見えないカレーほど徹底した管理のもとで作られていることが多く、必ずしも手抜きというわけではありません。
社長は、「具材の形を残さないのは、見た目ではなく安全を優先した結果。
特に作り置きをする店舗では、ぬるい温度帯(40〜60℃)が長時間続くと菌が繁殖しやすくなる」と補足しています。
つまり、“形を残さない=安全性を高めている”ということなのです。
レトルトと飲食店の違いもポイント
レトルトカレーは、密閉したパウチの状態で急速冷却されているため、具材を残したままでも安全に保存できます。
一方で、飲食店では大量調理・長時間提供という条件のもと、同じ管理は難しいのが現実です。
そのため、具材を減らして安全性を確保するのが現場の判断となります。
「具を後のせ」スタイルが増えている理由
最近では、野菜カレーなどで「素揚げした野菜を後のせする」スタイルも多く見られます。
これは、ルーと具を分けて衛生的に管理できるだけでなく、見た目の彩りや食感の面でもメリットがあります。
食中毒を防ぎつつ、見た目の満足感を保つ工夫として広まっている手法です。
まとめ:飲食店カレーの“具なし”は安全への配慮
飲食店のカレーに具が少ないのは、コスト削減だけが理由ではありません。
実際には、細菌の繁殖を防ぐための衛生管理上の工夫として“具なしカレー”が選ばれているのです。
ルーの中に具材が溶け込んでいたり、後のせトッピングで対応していたりと、各店が安全と美味しさの両立を模索しています。
「具がないからレトルトっぽい」と感じるかもしれませんが、そこには“安心して食べてもらうための知恵”が隠れているのです。