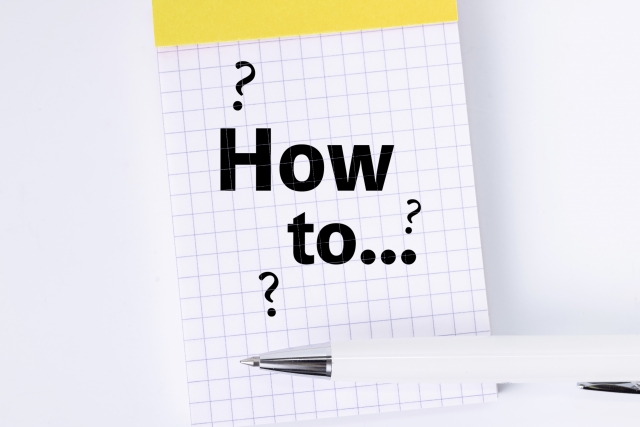「土用の丑の日」といえばウナギを思い浮かべる人も多いでしょうが、実はウナギの旬は夏ではなく冬だと言われています。では、なぜ真夏にウナギを食べる習慣が広まったのでしょうか。今回はウナギの旬や文化、食べるタイミングの違いについて解説します。
ウナギの「本当の旬」は冬
自然界のウナギは変温動物で、寒い時期には活動をほとんどしません。そのため、冬に備えて栄養を蓄えた晩秋から初冬にかけては、脂がのって最も美味しい時期とされています。
これが「ウナギの旬は冬」と言われる理由です。
ただし、現在市場に流通しているウナギの多くは養殖によるものです。
養殖場では水温が30度近くに保たれ、通年で活動できる環境にあるため、自然の旬はあまり関係なくなっています。養殖では、夏に向けて状態の良いウナギが出荷されるよう管理されているため、販売の最盛期も夏になります。
とはいえ、養殖のスタイルや出荷タイミングにはバラつきがあり、季節を問わず上質なウナギに出会える機会もあります。店先で「良いウナギが入りました」と勧められたら、季節にこだわらず楽しんでみるのも一興です。
なぜ夏にウナギを食べるのか
ウナギは縄文・弥生時代から食べられていたとされ、古代の遺跡から骨が出土しています。タンパク質やビタミン、カルシウムが豊富で、昔から滋養強壮に良い食材として重宝されてきました。
奈良時代には「夏バテに効く」とされ、夏にウナギを食べる風習があったことが記録に残されています。現在のような蒲焼きの形が定着したのは江戸時代で、この頃から「土用の丑の日」にウナギを食べるという習慣が広まったといわれています。
その背景には「丑の日には“う”のつくものを食べると良い」といった習わしがあり、それをきっかけに販売促進が行われたとする説もあります。真偽は定かではありませんが、夏の食文化として定着したのは事実です。
ウナギの流通と食文化
近年の稚魚の漁獲量は10〜20トンの間で推移しており、価格も2018年のピークからはやや下がりつつあるものの、依然として高値が続いています。
主な生産地は鹿児島県、愛知県、宮崎県、静岡県など。なかでも愛知県の「一色うなぎ」は地域ブランドとして名高く、宮崎県も近年生産量を伸ばしています。
調理法にも地域ごとの特色があります。たとえば東日本では「背開き」で蒸してから焼く関東風、西日本では「腹開き」で蒸さずに焼く関西風が主流。九州では甘めのタレを使い、「せいろ蒸し」など独自の食文化も発展しています。
まとめ
ウナギは古くから日本人の食文化に根付いており、旬とされる冬はもちろん、夏にも美味しく食べられるよう工夫が重ねられてきました。夏場のスタミナ食としての印象が強いウナギですが、季節を問わず、良質なものに出会えるチャンスはあります。地域の食文化や調理法の違いも含め、ウナギの魅力を多角的に楽しんでみてはいかがでしょうか。