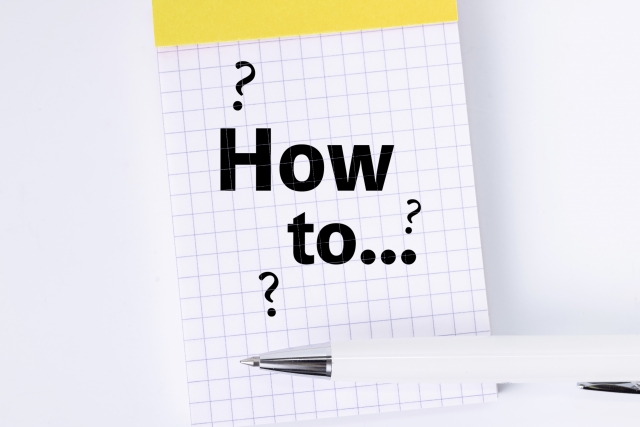この記事では、情熱的な画家「フィンセント・ファン・ゴッホ」の一生について、子ども時代から晩年、そして亡くなった後に名声を得るまでの経緯を詳細にご紹介します。
目次
フィンセント・ファン・ゴッホ:短くも輝かしい画家生活
フィンセント・ファン・ゴッホは19世紀後半に活躍したオランダ出身の画家で、特に「ひまわり」の油彩画で知られています。彼はフェルメールやダ・ヴィンチ、ピカソなどと同じく、日本でも非常に人気の高いアーティストの一人です。日本国内では定期的に彼の作品展が開催され、数十万人もの観客が訪れます。
フィンセント・ファン・ゴッホの人生は37年と短く、画家としてのキャリアも10年間にすぎませんでした。彼はその短い活動期間中に約850点の油彩画を制作しましたが、生前に売れたのは「赤い葡萄畑」ただ一点だけでした。
ゴッホの作品が広く評価され、売れ始めたのは彼の死後数十年が経ってからのことです。生前には評価されなかったゴッホですが、なぜ彼は画家として生計を立て続けることができたのでしょうか?そして、なぜ彼の作品は生前認められなかったのでしょうか?
以下では、ゴッホの挑戦に満ちた画家人生を、彼の幼少期から追ってみましょう。
フィンセント・ファン・ゴッホの幼少期と教育
オランダの画家、フィンセント・ファン・ゴッホの誕生
1853年3月30日、オランダ南部の小さな村ズンデルドにて、プロテスタントの牧師テオドルス・ファン・ゴッホとその妻コルネリアの間にフィンセント・ファン・ゴッホが生まれました。この地域は自然に恵まれ、風車や農場が点在する牧歌的な風景が広がっています。フィンセントはその後、世界で最も称賛される画家の一人に数えられるようになります。 フィンセントという名前は、一年前に同じ日に亡くなった彼の兄にちなんで名付けられました。ゴッホの両親は、故人の記憶を新たに生まれた子に託したのです。
ゴッホの成長と教育
ゴッホは少年期を自然豊かな環境で過ごし、幼い頃から一人で自然を散策することを好みました。母から絵を勧められたことがきっかけで、10歳から本格的に絵画に興じるようになります。彼は6人兄弟の中で特に絵の才能を発揮し、弟テオドルスとは特に親しく、後にテオはゴッホの芸術活動を支える最大の理解者となります。 父テオドルスは牧師としての職に加えて農業も行い、家族を支えました。ゴッホは13歳で学業に優れ、ズンデルトから20km離れたティルブルフにあるヴィレム2世校に入学しますが、入学後2年で突如退学し家に戻ってしまいます。その理由ははっきりしていませんが、金銭的な問題や対人関係の問題が原因とされています。 学校在籍中は、後に風景画家として名を馳せるコンスタント=コルネーリス・ハイスマンスから絵画の基礎を学びました。また、この時期に外国語の学習も行い、多方面での教養を深めていきます。 フィンセント・ファン・ゴッホの人生は短くも激動のものでしたが、彼の作品とその生涯は今日も多くの人々に影響を与え続けています。
フィンセント・ファン・ゴッホの初めての職と人生の転機
ゴッホの美術商としてのキャリアの始まり
1869年、フィンセント・ファン・ゴッホは、伯父の紹介でハーグの「グーピル商会」に就職しました。この商会は絵画を扱う画商で、オランダやフランスなどヨーロッパ各地に支店を構えていました。ゴッホ家には芸術商や軍事将校など社会的に成功した者が多く、フィンセントもこのコネクションを利用して美術商になる道を歩み始めました。 彼の職務は順調で、3年後には弟テオも同じグーピル商会に就職します。フィンセントは、弟と同じ職場で働けることに大きな喜びを感じ、テオに対する感動を手紙で伝えました。この兄弟間の手紙のやり取りは、フィンセントが亡くなるまで続き、現在も約700通の手紙が残されており、ゴッホの作品や人生を理解する上で貴重な資料となっています。
ゴッホのロンドンでの栄転と私生活
1873年、ゴッホはハーグ支店での優れた仕事ぶりが認められ、ロンドン支店への栄転が決まります。ロンドンでは博物館や公園で過ごすなど、プライベートの時間も充実していました。また、大衆芸術に興味を持ち、新聞のモノクロ版画や挿絵を約1000点も集めるほどでした。特に労働者をテーマにした版画や、チャールズ・ディケンズの小説に深い影響を受け、これが彼の生涯にわたる芸術観に影響を与えました。 しかし、ロンドン転勤直後、下宿先の女性「ウジェニー・ロワイエ」に恋をし、彼女に想いを告げるも、すでに婚約者がおり断られるという大失恋を経験します。この失恋はゴッホにとって大きな打撃となり、以降彼の仕事への熱意は著しく低下しました。
ゴッホの職を失うまでの道のり
周囲はゴッホの変化に気付き、彼の叔父は環境を変えるためパリ支店への転勤を命じますが、失恋の影響は深く、彼は聖職者を目指すべきかと悩み始めました。その後、無断で実家に帰省したことが問題視され、最終的にグーピル商会から解雇されることになります。この出来事はゴッホにとって新たな人生のスタートを意味していました。
フィンセント・ファン・ゴッホ:教師から伝道者への道
英国での教職と伝道活動の始まり
1876年、フィンセント・ファン・ゴッホは23歳でグーピル商会を解雇された後、イギリスのラムズゲイトにある寄宿学校で語学教師としての職を得ます。教師としての彼の能力は高く評価されましたが、生徒への過度の献身や学校の利益に反する行動が原因で、わずか一年でその職を失います。 次にゴッホが頼ったのは、以前の職場で知り合ったアイルワースの牧師ジョーンズでした。ジョーンズの助けを借りて、彼は学校の補助教員兼伝道師としての職を得ることができました。1876年11月、ゴッホは教会で初めての説教を行い、これが自身の天職であるとの確信を深めました。 しかしながら、ゴッホの伝道活動は極端で、全ての持ち物を貧しい人々に分け与えるほどでした。この過酷な生活スタイルが彼の健康を損ね、最終的には伝道師としての資格も停止されてしまいます。この出来事がきっかけで、彼は失意のうちにオランダへ帰国することになります。
神学への道と挫折
オランダへ帰国したゴッホは、両親の住むエッテンへ向かい、一時は地元の書店で働き始めますが、牧師になるために聖書研究に没頭し、仕事をおろそかにしてしまいます。このため、ゴッホは書店の仕事も短期間で辞め、アムステルダムの神学大学での学びを目指す決意を固めます。 親族の支援を受けてアムステルダムで勉強を始めたゴッホは、当初は受験勉強に励みますが、やがて教義への疑問や学問的な困難に直面します。『貧しい人々を救うために何故多言語を学ばなければならないのか』という疑問から、やる気を失い、最終的には神学の道を諦めてしまいます。 この段階で、ゴッホは画家としての道を歩み始めることを決意します。これが後に世界的に有名な画家となるフィンセント・ファン・ゴッホの芸術家としてのスタート地点となりました。
フィンセント・ファン・ゴッホ:伝道師から画家への転機
ベルギーのボリナージュでの挑戦
1878年、牧師の資格を持たないものの、貧しい人々への救済活動に情熱を燃やすフィンセント・ファン・ゴッホは、ベルギー南部の炭鉱地域ボリナージュに臨時説教師として赴任しました。ここで彼は、過度なまでに病人や負傷者へのケアに献身し、その行動が原因で監視委員会から臨時説教師としての資格を剥奪されました。ゴッホにとって、これはキリストの教えを忠実に実践しているだけのことでしたが、周囲には非常識な行動と映りました。
絵画への情熱の芽生え
資格を失った後もゴッホはボリナージュ地域に約1年間留まり、その間、坑夫や酒場などの日常をスケッチし続けました。これらのスケッチが彼の唯一の慰めであり、やがて絵画への真の情熱を見出すこととなります。1880年の夏、27歳のゴッホはプロの画家としての道を歩む決意を固めました。この頃から、彼を支える弟テオからの仕送りも始まります。
エッテンでの再起と挫折
画家としてのキャリアを追求する決意を新たにしたゴッホは、ブリュッセルでの短期間の滞在を経て、1881年4月に再び両親の住むエッテンに戻りました。エッテンでは、独学でデッサン技術を磨き、ジャン=フランソワ・ミレーの作品を模写するなど、絵画の基礎固めに励みました。しかし、ゴッホは再び私生活での問題に直面します。
失恋と家族との確執
エッテン滞在中、ゴッホは未亡人で従姉のケー・フォスに熱烈な恋愛感情を抱きますが、彼女には全く相手にされず、その失恋はゴッホをさらに精神的に不安定にしました。彼はケーを追ってアムステルダムまで行きますが、彼女の両親に会うことすら拒否され、自分の手をランプの炎にかざしてまで彼女と話す機会を求めました。この過激な行動は家族の名誉を傷つけ、父との間にも深刻な亀裂を生じさせました。 1881年のクリスマスには、ゴッホは家族と宗教観を巡って激しく争い、結局家を出ることになりました。弟テオはゴッホの自立を支援することを約束しますが、彼の行動には怒りと同時に、兄の芸術への才能への期待も含まれていました。
フィンセント・ファン・ゴッホのハーグ時代:愛と孤立
ハーグでの新生活と師弟関係の破綻
フィンセント・ファン・ゴッホが家を出た後、彼が頼ったのはハーグに住む義理の従兄であり画家のアントン・マウフェでした。マウフェはゴッホを暖かく迎え入れ、彼に油絵と水彩画の技術を教え、さらには生活の面でも支援を惜しまなかった。ゴッホはマウフェのもとで小さなアトリエを構え、近代都市の風景を描き始めましたが、やがてマウフェとの関係はゴッホの一方的な意見や、受け入れがたい私生活が原因で短期間で終わりを迎えました。
シーンとの同棲と家族との断絶
この頃、ゴッホは冬の街角で見かけた年上の娼婦シーンを同情から自宅に招き入れ、やがて彼女と同棲を始めました。シーンは子持ちでありながら生計を立てるために娼婦としても働いていました。当初は彼女を肖像画のモデルとして迎え入れたゴッホでしたが、次第に彼の感情は愛情へと変化し、彼女の全てを受け入れ結婚を決意します。この時期に描かれた「悲しみ(Sorrow)」や「砂地の木の根」は、彼の代表作として知られるようになりました。 しかし、ゴッホの穏やかな生活は長続きせず、父テオドルスが同棲を解消するようにと訪れたことで、家族との間にさらなる溝が生じました。弟テオもこの状況に賛同できず、一時的に仕送りを停止しました。最終的にゴッホはテオの説得を受け入れ、シーンとの同棲を解消しました。
農村への移住と再出発
ゴッホは1883年9月にドレンテ地方へ移住しますが、経済的困難から再び両親を頼ることになります。30歳を迎えたゴッホは、両親が新たに赴任したドイツ国境近くのニューネンへと向かい、再び絵画に専念する道を模索し始めました。この転機は、彼の芸術家としての更なる成長に繋がる重要な期間となりました。
ニューネンでの画家としての転機
ニューネンの家とアトリエ
フィンセント・ファン・ゴッホは、家族との喧嘩別れから約2年ぶりにニューネンに帰省しました。父テオドルスはゴッホに家の一部をアトリエとして使うことを許可し、これが彼の画家としての飛躍のきっかけとなりました。当初、ゴッホは暗い色調の作品を多く描いており、これは師であるアントン・マウフェやハーグ派の画家たちの影響を受けていたためです。
「ジャガイモを食べる人々」とその影響
ゴッホは、ニューネンで風景画や肖像画、農民の生活をリアルに描いた作品を次々と完成させました。「ジャガイモを食べる人々」はこの時期に描かれ、ゴッホ初期の代表作となりました。この作品は、彼の芸術家としての真価を示すものであり、後の作品にも大きな影響を与えました。
個人的な試練と家族との関係
しかし、ゴッホの生活は再び試練に見舞われます。隣に住む年上の女性、マルホット・ベーヘマンがゴッホに恋をし、彼女の精神病が悪化して自殺を図る事件が発生しました。
さらに、1885年には父テオドルスが急逝するという不幸がゴッホを襲い、これにより家族との間の緊張がさらに高まりました。
ゴッホと父は生前、言葉での理解が得られなかったが、最終的には父はゴッホの画家としての道を支援していました。
愛と誤解、そして新たな旅立ち
ゴッホの私生活では、ある女性を妊娠させたという根も葉もない噂が広がり、ニューネンでの居心地の悪さを感じ始めます。
この噂は完全な誤解でしたが、ゴッホはこれを機に故郷を離れる決意を固めました。
1883年の終わりにゴッホはドレンテへ移住し、その後、両親の新たな赴任地であるニューネンへと向かいました。これがゴッホが故郷オランダに戻る最後の時となりました。
パリにおけるゴッホ:芸術と浮世絵の出会い
ゴッホとゴーギャン:共鳴する魂
パリに移り住んだ後のゴッホは、当時まだ無名であった画家ポール・ゴーギャンとの深い友情を築きます。二人は日本の浮世絵に共通の興味を持ち、安価で手に入る浮世絵版画を積極的に収集しました。この時期、パリでは万国博覧会の影響もあり、日本趣味(ジャポニズム)が流行しており、多くの芸術家が日本の美術に魅了されていました。
浮世絵からのインスピレーション
ゴッホは、点描画の実験など、様々な画法を試しながらも、浮世絵からの影響を強く受けていました。そのカラフルな色使いや大胆な筆遣い、はっきりとした輪郭線は、彼の画風に新たな可能性をもたらしました。浮世絵の技法を取り入れ、彼は作品「花魁」や「梅の開花」など、多くの浮世絵を模写し始めました。 【浮世絵からの作品】
- 花魁 – フィンセント・ファン・ゴッホによる模写
- 梅の開花 – フィンセント・ファン・ゴッホによる模写
この時期のゴッホの作品には、浮世絵の技法が色濃く反映されており、「タンギー爺さん」などのオリジナル作品も日本の影響下にあります。
トラブルと新たな旅立ち
パリでの生活はゴッホにとって精神的な疲労が蓄積されていきました。芸術家としての評価は高まる一方で、絵が売れず、大量のアブサンを飲むなどして日々を送りました。これが原因で周囲の芸術家たちとの関係も悪化し、孤立が深まっていきます。さらに、弟テオとの関係もストレスにより悪化しましたが、テオはゴッホの才能を信じ続け、経済的に支援していました。 最終的にゴッホはパリの生活に疲れ、1888年2月、アルルへの移住を決意します。パリでの2年間は芸術家としての成長には寄与しましたが、精神的には非常に困難な時期であったと言えるでしょう。
アルルでのゴッホ:希望から絶望へ
南フランスの田園地帯で新たなスタート
1888年2月、ゴッホは活気に満ちたパリを離れ、フランス南部の田園地帯、アルルに移住しました。彼はここで、浮世絵に見る日本の色彩豊かな景観を感じ取りながら新しい生活を始めました。アルル到着後、ゴッホは黄色い外観の家に魅了され、この建物を「黄色い家」と名付け、数部屋を借りて生活をスタートさせます。この家は後に彼の絵画の中で重要なモチーフとなり、現在も彼の代表作として知られています。 【黄色い家の描写】 黄色い家 {{PD-US}} – image source by WIKIMEDIA
創作の充実と新たな友人
アルルでの生活はゴッホにとって創造的な充実をもたらし、彼は肉体的、精神的にも回復していきました。アルルの陽光と風土が彼の作品に新たな明るさと力強さをもたらし、「アルルの跳ね橋」や「花咲く桃の木」などの作品を生み出しました。 【アルルでの主要な作品】
アルルでは、郵便配達員ジョゼフ・ルーランとも親しくなり、彼とその家族の肖像を数多く描きました。これらの交流がゴッホにとって大きな支えとなりました。 【ジョゼフ・ルーランの肖像】 郵便夫ジョゼフ・ルーランの肖像 {{PD-US}} – image source by WIKIMEDIA
ゴーギャンとの期待と裏切り
ゴッホはアルルで芸術家コミュニティを形成する夢を抱いており、ゴーギャンを含む他の画家たちを招待しました。ゴッホはゴーギャンの到着を前に「ひまわり」のシリーズを描き始め、その準備に熱中しました。しかし、ゴーギャンとの共同生活は、互いの芸術観や性格の不一致からすぐに破綻しました。 【ゴーギャンの自画像と「ひまわり」】 ゴーギャンの自画像
絶望への転落
ゴッホとゴーギャンの関係が破綻した後、ゴッホは精神的に不安定となり、有名な耳を切る事件を引き起こしました。この出来事は彼のアルルでの生活を大きく変え、最終的には精神病院への入院につながりました。この時期は彼にとって非常に困難で、多くの挑戦に直面しましたが、その中で多くの重要な作品を残しました。
サン・レミ療養院での療養生活と芸術的充実
サン・レミでの静かな日々
1888年に精神的な崩壊を経験したフィンセント・ファン・ゴッホは、療養のためサン・レミの療養院に入院しました。ここでの生活は厳しい発作に見舞われることもありましたが、健康が許す限り、彼は外で絵を描くことができるほどでした。この期間、彼は多くの作品を制作し、特に「糸杉のある麦畑」などの風景画は高い評価を受けています。 【療養中の制作活動】 糸杉のある麦畑 {{PD-US}} – image source by WIKIMEDIA
安定期と創作の充実
ゴッホはサン・レミ療養院で約130点の作品を描きました。彼の心情が比較的安定している時期には、「星月夜」や「糸杉と星の見える道」など、後に大きな評価を受ける作品を生み出しています。 【精神安定時の代表作】
- 星月夜 – ニューヨーク近代美術館
- 糸杉と星の見える道
これらの作品は、ゴッホの内面の葛藤や美的探求が色濃く反映されたもので、彼の芸術的な到達点を示しています。
家族との連絡と支援の続行
サン・レミでのゴッホの生活は、弟テオの経済的支援によって支えられていました。テオはゴッホが健康を取り戻すことを願い、定期的に手紙を交わし、励まし続けました。また、テオの第一子誕生を祝して描かれた「花咲くアーモンドの木の枝」は、この時期の穏やかな心象を映し出しています。 【テオへの祝福として描かれた作品】 花咲くアーモンドの木の枝 {{PD-US}} – image source by WIKIMEDIA
精神的な不安定と創作の狭間で
サン・レミ療養院での生活はゴッホにとって一時的な避難所であり、彼の創作意欲をかき立てる場でもありました。しかし、彼の健康状態は依然として不安定で、テオや医師からの助言を受け、より穏やかな環境を求めて1890年5月にオヴェールへ移住することを決意します。この移動はゴッホの人生において新たな章の始まりであり、彼の芸術旅程の最終章を飾ることになります。
ゴッホの最後の70日間と自殺の真相 – オヴェール時代
新しい土地での新しい出発
ゴッホはサン・レミからオヴェールに向かう途中、パリに立ち寄り、弟テオとその妻ヨハンナ、そして生まれたばかりの甥フィンセントに会うことができました。1890年5月20日、ゴッホはパリを離れ、オヴェールに到着し、ラヴー亭という宿屋に滞在しました。
ガジェ医師との出会いと治療
オヴェールでゴッホは、画家のピサロに紹介されたガジェ医師の治療を受けました。ガジェは医師であり絵画愛好家でもあり、二人はすぐに友人となりました。しかし、ゴッホは手紙の中で、ガジェ医師に対して医療以外の分野では少し頼りないと感じていたようです。
【オヴェールでの主要作品】
ガジェ医師はゴッホの治療に尽力しましたが、ゴッホの深い精神的な苦しみを完全に癒すことはできませんでした。ゴッホは自身を社会不適合者で経済的にも自立できないと感じ、自己嫌悪に陥っていました。
最期の日々と自殺
1890年7月27日、ゴッホはオヴェール近くの小麦畑で拳銃で胸を撃ち、自殺を図りました。急所を外れたため、彼はまだ息があり、宿まで這い戻ることができました。その後2日間生き延び、テオが駆けつける中、1890年7月29日に37歳で息を引き取りました。
テオの苦悩と死
ゴッホの死はテオに大きな衝撃を与え、精神的に大きな負担となりました。テオは兄の死からわずか半年後に、33歳の若さで亡くなります。最終的な死因は、免疫力低下による腎臓病や心臓病とされています。
自殺の真相に関する議論
ゴッホの自殺については多くの謎が残っています。実際に彼が撃たれた瞬間を目撃した人はおらず、銃弾の角度が不自然だという指摘もあります。そのため、一部では他殺説も提唱されています。ゴッホの死については、彼の伝記映画「永遠の門」でも、他殺説が描かれています。
死後に高まる名声と作品評価
生前に始まった評価
フィンセント・ファン・ゴッホは、死後に評価された画家として知られていますが、実際にはサン・レミの療養院に入院していた頃から、彼の作品に対する評価が高まり始めていました。1890年1月から2月にかけて開催された20人会展で、ベルギーの画家アンナ・ボッホがゴッホの「赤い葡萄畑」を購入しました。アンナはゴッホの知人の姉であり、その関係もあって作品が売れやすかった側面もありますが、正式な場でゴッホ作品が初めて売れた瞬間でした。
アンデパンダン展と初期の評価
さらに、1890年3月に開催されたアンデパンダン展では、弟テオが「星月夜」を含む10点のゴッホ作品を出品し、専門家や同業者たちから高い評価を受けました。この頃から、ゴッホの作品に対する好意的な論評が雑誌に掲載され始めます。しかし、極度にネガティブになっていたゴッホは自身の作品がまだ評価に値しないと考え、これらの好意的な評価を素直に受け止めることができませんでした。
死後の評価の高まり
ゴッホはその数ヶ月後に亡くなりましたが、その後も様々な展覧会で毎年のように作品が出品され、死後10年間で評価が着実に高まっていきました。特に1904年にアムステルダム市立美術館で開催された展示会では、約500点ものゴッホ作品が出展され、オランダ国内および周辺国での知名度が飛躍的に高まりました。
ヨハンナの尽力と国際的な認知
ゴッホの作品が世界的に知られるようになったのは、テオの妻ヨハンナの尽力によるところが大きいです。ヨハンナはゴッホとテオの手紙のやり取りに魅せられ、それらを年代順に整理し、1914年に3冊の本として出版しました。この本は世界中で読まれ、1920年代頃までにはゴッホ作品が国際的に認められるようになりました。
ゴッホ美術館と日本での影響
20世紀半ばにはゴッホ財団が設立され、市と政府の援助により、オランダのアムステルダムにゴッホ美術館が設立されました。テオの元に残った作品はほぼこの美術館に寄贈され、現在では世界で最も多くのゴッホ作品(約200点)を収蔵する場所となっています。
1958年10月15日には、日本初のゴッホ展が東京で開催され、約1ヶ月で45万人を動員しました。バブル期の1989年には、ゴッホの代表作「ひまわり」が安田火災海上保険(現・損保ジャパン)によって約53億円(現在の為替換算で約58億円)で落札されました。1990年には、大昭和製紙(現・日本製紙)の名誉会長が「医師ガジェの肖像」を約125億円で落札し、世界を驚かせました。
これらの出来事を通じて、ゴッホは日本で最も有名な画家の一人として不動の地位を確立しています。