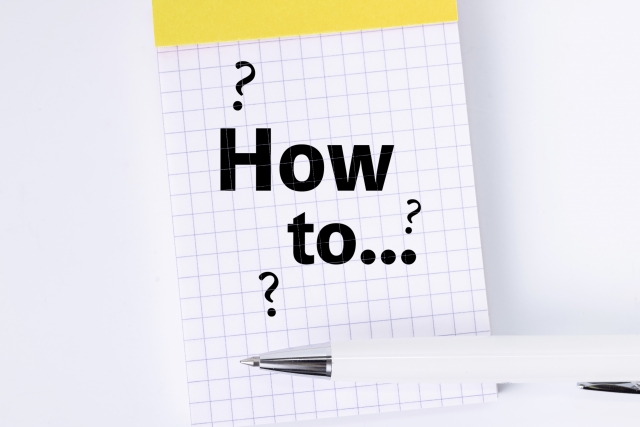スマートフォンやタブレットの普及により、電子書籍はすっかり一般的な読書スタイルとして定着しました。
かつては「紙で読まないと落ち着かない」と感じていた人でも、今では端末ひとつで読める便利さから電子書籍を併用するケースが増えています。
では、著者にとってはどのような違いがあるのでしょうか。
ここでは、紙の書籍と電子書籍、それぞれの印税率や売上構造について詳しく見ていきます。
電子書籍と紙の書籍の印税率の違い
まず印税の仕組みから整理していきましょう。
一般的に、紙の書籍の印税率はおよそ10%とされています。
これは「刷った部数」に対して発生するため、初版と重版が中心となり、一度きりの収入になることが多いのが特徴です。
一方、電子書籍の場合は印税率が大きく異なります。
個人出版では30〜70%ほどの高い割合が設定されることもあり、紙よりも著者への還元率が高くなる傾向があります。
出版社経由と個人出版での違い
ただし出版社を通して電子書籍を販売する場合、印税率は契約内容によって異なります。
紙の書籍より高いケースもあれば、そこまで差が出ない場合もあります。
電子書籍の大きな特徴は、売れた分だけ毎月収入が入る点です。
印刷コストがかからないため、販売された冊数に応じて収益が継続的に入ってくる仕組みになっています。
対して紙の書籍は、主に初版の発行時点で印税の大部分が確定するため、継続収入にはつながりにくい構造といえるでしょう。
電子書籍の価格が紙より安い理由
電子書籍は紙の本よりも価格が低く設定されていることが多く、
「どうしてこんなに安いのだろう?」と疑問に思ったことがある人も少なくありません。
電子書籍の値段が安い背景
大きな理由のひとつは、電子書籍市場の拡大戦略です。
とくにAmazonなどのプラットフォーマーは、電子書籍の読者を増やすために、
出版社に支払いをしながらもユーザーに低価格で提供する方針を取っています。
短期的には利益が小さくても、読者数が増えれば長期的に市場を支配できるという狙いがあり、
結果としてユーザー側はリーズナブルに電子書籍を購入できる状況が生まれているのです。
電子書籍と紙の書籍の売上はどちらが高い?
では実際の売上規模はどうなのでしょうか。
近年の出版市場データをもとに比較してみます。
紙の出版市場の現状
全国出版協会が公表した2017年のデータでは、紙の本と雑誌を合わせた市場規模は約1兆3700億円。
依然として紙媒体は非常に大きな市場を持っていますが、前年比では6.9%減となり、13年連続で縮小しています。
内訳は、書籍が7152億円(前年比3%減)、雑誌が6548億円(前年比10.8%減)。
紙媒体全体が徐々に減少していることが読み取れます。
電子書籍市場は急成長中
一方、電子書籍・電子雑誌・電子コミックなどを合わせた電子市場は2215億円で、前年比16%増と急拡大しています。
特に伸びが大きいのがコミック分野で、電子コミックは1711億円(17.2%増)と市場をけん引しています。
電子書籍(290億円)と電子雑誌(214億円)も、それぞれ10%以上の成長を記録しています。
全体では紙の出版物にまだ大きく及びませんが、
伸び率という点では電子のほうが圧倒的に上回っており、今後も市場拡大が続くと見られています。
まとめ
紙の書籍と電子書籍は、印税や売上構造に大きな違いがあります。
- 紙の書籍:印税は主に初版時に支払われ、一般的に10%前後
- 電子書籍:30〜70%と高い印税率になることもあり、売れた分だけ毎月収入が入る
- 電子書籍は低価格で販売されることが多く、市場拡大戦略の一環
- 売上規模は依然として紙が圧倒的だが、電子市場は急成長中
読者の選択肢が増える中で、著者にとっても販売手段が広がりつつある今、
紙と電子をうまく使い分けることでより多くの読者に届けることが可能になっています。