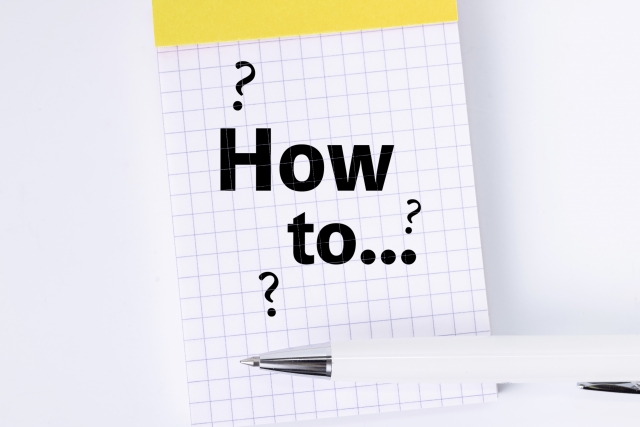受胎告知とは
受胎告知とは、キリスト教の重要な信仰の一環であり、聖母マリアが救世主とされるイエス・キリストを懐胎するという神聖な知らせを、大天使ガブリエルが直接マリアに伝えた出来事です。
この事件はキリスト教の文献である「新約聖書」の「ルカの福音書」に詳しく記されており、聖書内で「聖告」とも呼ばれています。
この出来事はキリスト教の美術においても頻繁に表現されるテーマとなっています。
具体的なエピソードは、「ルカの福音書」の1章26節から38節に記載されています。
記述によると、神の使いであるガブリエルがナザレというガリラヤの町に派遣され、そこでダビデの家系に属するヨセフと婚約していた処女マリアに出現します。ガブリエルはマリアに神の恵みが与えられていること、そして彼女が男子を懐妊することを告げます。
その子はイエスと名付けられ、非常に高い地位につくとされ、「いと高き方の子」と呼ばれることになります。
マリアが自らが未だ男性を知らないことから、この告知に対して当初は困惑しましたが、ガブリエルは聖霊が彼女に降りてくることを説明し、神の計画の一環として、彼女がこの奇跡を受け入れることになります。
さらに、マリアの親類エリサベツも高齢にもかかわらず男子を懐妊している事実が示され、神にとって不可能なことはないと伝えられます。
最終的にマリアは神の計画に同意し、「主のはしため」として従うことを宣言し、ガブリエルは去っていきます。
この受胎告知は、キリストの誕生を9ヶ月前にあたる3月25日に行われたとされ、この日はキリスト教圏では「お告げの祭り」として祝われています。
この祭りはキリストの人間としての生を始めた瞬間を記念し、信徒にとって大変重要な意味を持つ日です。
絵画における『受胎告知』の表現と意義
『受胎告知』はキリスト教の信仰において中心的なテーマの一つであり、その重要性から多くの聖堂や礼拝堂にその情景が描かれています。 このテーマでは、聖母マリア、大天使ガブリエル、そして聖霊を象徴する鳩が主要な要素として描かれます。
また、マリアの純潔を象徴する百合の花や、エルサレムの神殿で育ったという伝承にちなんだ糸巻棒や籠が描かれることもあります。
さらに、聖書が頻繁に描かれ、その中でマリアが読んでいる部分は「イザヤ書」から「見よ、処女がみごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと名づける」という予言が指摘されています。
絵画には「Ave Maria(マリアよ、おめでとう)」や「Ave gratia plena Dominus tecum(恵まれた方、主が共におられます)」などの言葉がしばしば含まれ、マリアの聖なる受胎を祝福する表現がされています。
例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチの『受胎告知』は、ウフィツィ美術館に収蔵されており、かつては修道院でドメニコ・ギルランダイオの作品とされていたこの絵画は、ルネサンス時代の屋内を舞台にして描かれています。
同様に、フラ・アンジェリコの『受胎告知』はフィレンツェのサン・マルコ修道院にある壁画で、マリアのおそれととまどう表情を捉えた作品です。
ヤコポ・ダ・ポントルモの作品では、マリアが立って描かれ、ガブリエルから身体を背ける姿勢で戸惑いや恐れを表現しています。この作品には、キリストの死を見つめるマリアが中心的なテーマとなっています。
これらの作品を通じて、『受胎告知』がいかにキリスト教芸術において重要な位置を占めているかが理解できます。
聖書のテキストだけでなく、視覚的な表現もまた信者にとって理解を深める手段となっているのです。
他の画家による『受胎告知』の描写
サンドロ・ボッティチェッリによる『受胎告知』は1489年頃に描かれ、現在ウフィツィ美術館に収蔵されています。
この作品はボッティチェッリ特有の繊細なタッチと美しい色彩で知られ、聖母マリアと大天使ガブリエルの交流が優雅に表現されています。
また、エル・グレコが16世紀末に描いた『受胎告知』は、大原美術館に展示されており、彼の特徴的な表現主義的スタイルで描かれています。この作品では、エル・グレコ独自の色彩感と動的なフォルムがマリアの神秘的な体験を強調しています。