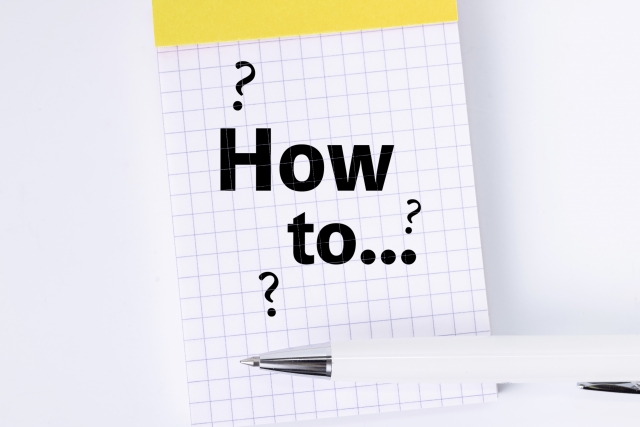街を歩いていると、どこにでもあるインドカレー屋。
ナン食べ放題のランチや香辛料の香りが漂う店内は、多くの人にとって身近な存在です。
しかし、よく考えてみると「インドカレー屋って、なぜ潰れないのだろう?」と感じたことはありませんか?
実はそこには、日本の外食業界とは少し異なる独自の経営戦略と強いネットワークがあるのです。
この記事では、インドカレー屋が長く続く理由をわかりやすく解説します。
インドカレー屋の多くは「ネパール人経営」だった
「インドカレー屋」と聞くと、本場インド人が経営しているイメージを持つ人が多いかもしれません。
しかし、日本にある多くのインドカレー屋は、実はネパール人が経営・調理しているお店です。
なぜネパール人が多いのか?
ネパールはインドと文化的に近く、料理も似ているため、インド料理を提供するノウハウを持っている人が多いのが特徴です。
さらに、日本ではネパール人が比較的ビザを取得しやすく、同郷のネットワークを活用して店を開くケースが多いのです。
経営者やシェフの多くは親族・友人関係でつながっており、調理技術や経営ノウハウ、人材を共有することで低コストで安定した経営を実現しています。
「ナン食べ放題ランチ」が安定集客のカギ
インドカレー屋といえば、お昼のナン食べ放題ランチが定番です。
このランチセットは、実は非常に利益率の高い戦略商品になっています。
ナンは原価が安いから食べ放題にできる
ナンは小麦粉と水、油などで簡単に作れるため、1枚あたりの原価が非常に安いのが特徴です。
そのため、おかわり自由にしても利益が減りにくく、「コスパの良さ」でお客さんを引きつけられます。
ランチは回転率が高く、固定客がつきやすい
安くてボリュームのあるランチセットは、近隣の会社員や学生のリピーター獲得に効果的です。
毎日通う常連客が増えることで、平日昼間の安定した売上につながっています。
テイクアウト・デリバリーが強いのも特徴
インドカレーはテイクアウトやデリバリーと相性が抜群です。
辛さを調整でき、冷めてもおいしさが保たれるため、自宅や職場での需要が高いのです。
コロナ以前からテイクアウト対応が進んでいた
多くのインドカレー屋では、コロナ禍以前から「持ち帰りOK」の文化が根付いていました。
そのため、外出自粛の波が来ても、いち早くデリバリー・テイクアウトに移行でき、売上を維持できたのです。
デリバリーサービスで新規顧客を獲得
近年ではUber Eatsや出前館などの配達サービスを積極的に導入し、新規顧客層を広げています。
立地に関係なく注文が入るため、駅から離れた店舗でも集客が可能です。
家賃が安い立地+シンプルな内装で経費を抑える
多くのインドカレー屋は、少し目立たない路地裏や雑居ビルの1階など、比較的家賃の安い物件に出店しています。
内装も派手な装飾ではなく、テーブルと椅子を並べただけのシンプルな造りが多いのが特徴です。
こうした固定費を抑える工夫が、利益を確保しやすい体制を作っています。
同郷コミュニティによる「経営の引き継ぎ」
インドカレー屋が潰れない最大の理由の一つが、ネパール人コミュニティによる経営の継承システムです。
経営者が変わっても店は続く
経営者が帰国する際や引退する際は、親戚や知人にそのまま店を引き継ぐケースが多く見られます。
ゼロから新しく店を始めるよりも、既存の店舗をそのまま引き継ぐことでリスクを最小限にできます。
そのため、外から見ると「長く続いている店」に見えても、実は経営者が何度か交代していることも珍しくありません。
夜は居酒屋スタイルで高利益を確保
インドカレー屋は夜になると、ビールやタンドリーチキンを楽しむ居酒屋的なスタイルに変わります。
お酒の提供は利益率が高く、ランチで薄利だった分を夜営業でしっかり回収する仕組みです。
特に常連客がグループで訪れることで、客単価が大きく上がり、経営の安定につながっています。
まとめ|インドカレー屋は「低コスト×固定客×ネットワーク」で強い
インドカレー屋が潰れない理由は、単なる味の良さではなく、以下のようなビジネスモデルの強さにあります。
- ネパール人コミュニティによる経営ノウハウの共有
- ランチタイムの高回転×ナン食べ放題による固定客獲得
- テイクアウト・デリバリーによる売上の分散
- 家賃・内装費を抑えた低コスト経営
- 経営継承による長期的な店舗存続
- 夜営業で高利益を確保
つまり、インドカレー屋は薄利多売と強いコミュニティの両輪で支えられているのです。
これが、なかなか潰れない最大の理由といえるでしょう。